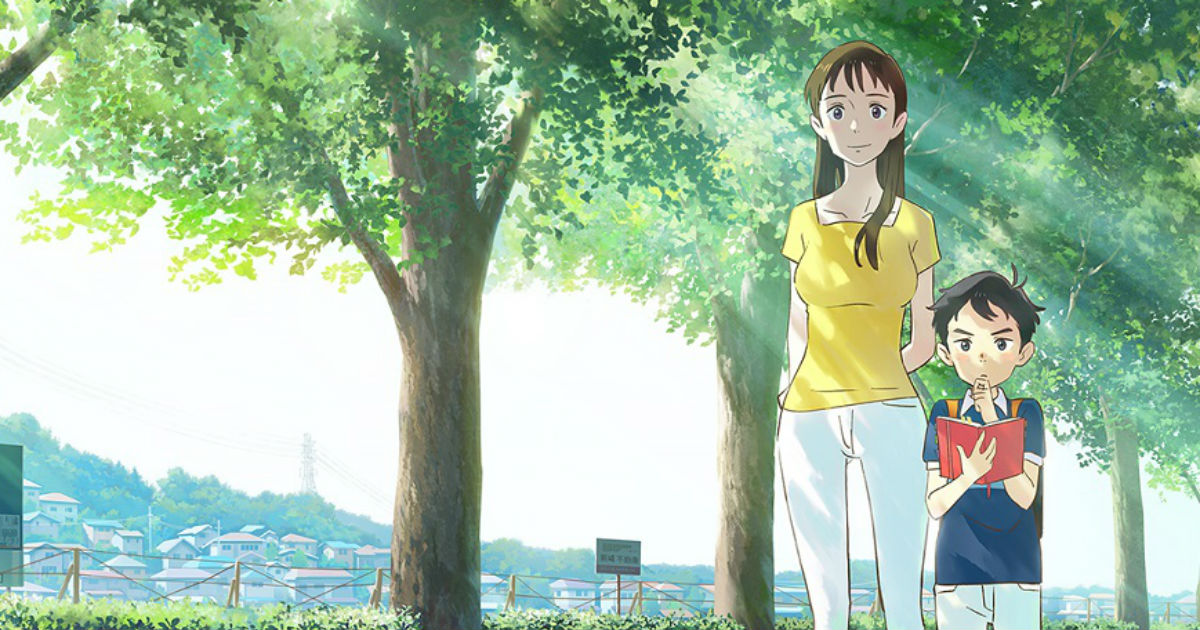監督:ジアド・ドゥエイリ
出演:アデル・カラム、カメル・エル・バシャ、リタ・ハーエク、クリスティーン・シュウェイリー、カミール・サラーメ、ディアマンド・アブ・アブード
原題:L’insulte
制作:レバノン、フランス/2017
URL:http://longride.jp/insult/
場所:TOHOシネマズ・シャンテ
2009年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で観たエリアーン・ラヘブ監督の『されど、レバノン』は、キリスト教マロン派を信仰する監督から見たレバノンと云う国の、宗教的にも民族的にも複雑さを抱える国の実情をアジアの東の端にいる我々にも知らしめてくれるドキュメンタリーだった。で、この映画の中で、狂信的なキリスト教民兵(レバノン軍団)がイエス・キリストの名において「キリスト教徒のコミュニティを守る」というスローガンのもとで、イスラム教徒、パレスチナ人、シリア人、および自分たち以外のキリスト教徒を敵対視するシーンが出てきたときに、イスラム教徒はわかるんだけど、パレスチナ人を名指しして排斥する理由がいまいちピンとこなかった。
ジアド・ドゥエイリ監督の『判決、ふたつの希望』は、キリスト教マロン派のレバノン人男性とパレスチナ難民の男性との口論がきっかけで起きる裁判を描いた映画だった。この映画を観て、レバノン国内の難民キャンプなどにいるパレスチナ人に対しての国内感情が決して良いものではなく、どこか差別的な感情があることに驚いた。イスラエルへの反発感情から単純にパレスチナ人擁護になるなんてことを考えていた自分がバカだった。でも、パレスチナ人たちが自分たちを排斥する人たちに向かって「シオニスト!」と叫んでいるシーンは、いやいや、そんな短絡的な、と笑ってしまった、
映画のストーリーでは裁判を重ねるうちに、次第にキリスト教のレバノン人男性がパレスチナ人を嫌う理由が判明して行き、彼が父親とともに1976年1月20日に起きた「ダムールの虐殺」の被害者であることが明らかになって行く過程がサスペンスフルですごく面白かった。レバノンでは、1976年1月18日の「カランティナの虐殺」(キリスト教徒の民兵組織がベイルート東部のカランティナ地区のパレスチナ人とイスラム教徒を殺害)、1976年1月20日の「ダムールの虐殺」(レバノン国民運動(LNM)と提携したパレスチナ人の民兵がダムールの村のキリスト教徒を殺害)、1976年8月12日の「テルザアタルの虐殺」(キリスト教徒の民兵がテルザアタルの難民キャンプに侵入してパレスチナ難民を殺害)と内戦時に3度も虐殺があって、この時のわだかまりがキリスト教徒やイスラム教徒、そしてパレスチナ人のあいだにまだまだくすぶっていると云う事実が怖くもあった。レバノンもシリアのような状態になる可能性を充分に秘めているのだった。
ただ、映画としては、伏線なしの衝撃的な事実判明はちょっとやりすぎな感じがしないでもなく、中東の国の映画と云うよりも、ハリウッド映画を真似た韓国映画あたりのアグレッシブさをおもいだしたりもしてしまった。
→ジアド・ドゥエイリ→アデル・カラム→レバノン、フランス/2017→TOHOシネマズ・シャンテ→★★★★