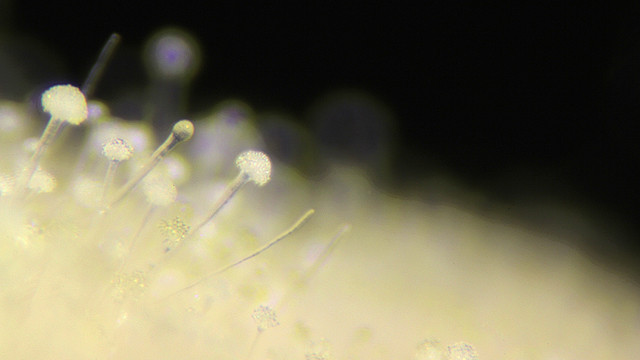監督:フレデリック・ワイズマン
出演:ボストンのベス・イスラエル病院に運び込まれた人びと
原題:Near Death
制作:アメリカ/1989
URL:
場所:シネマヴェーラ渋谷
ついにフレデリック・ワイズマンの6時間にも及ぶ映画を観た。
ボストンにあるベス・イスラエル病院の集中治療室(ICU)に運び込まれた緊急患者に対して、医師、看護婦がどのような対処をし、処置を施したかを延々とカメラで追いかけたドキュメンタリー映画。
この6時間にも及ぶフィルムのほとんどが、医師が患者本人や家族に対して病状を説明するシーンと、今後の治療の方向性を患者、家族に確認するシーンに費やしていた。多くの患者が微妙な選択を迫られる状況にあるために、その説明には繊細さが必要で、難しい医学用語をなるべく使わずに、相手のペースに合わせてゆっくりと丁寧に話す担当医師の姿をしっかりとカメラは捉えている。意識はあるけれど話すことの出来ない患者の表情や、一縷の望みにすがろうとする家族の表情なども合わせてワンカットで撮るので、まるで自分がその患者や家族になったかのような気持ちに陥り、ピーンと張りつめた緊張の連続の6時間だった。はじめは映画時間の長さに飽きるのではないかとおもったけど、患者と一緒に死と向き合わなければならない状態に飽きるはずもなく、最後まで画面を凝視したまま時間は過ぎ去って行った。
映画に登場する患者は主に次の4人。
1人目
John Gavin(72)。心臓病患者ギャビン氏。心臓病も末期に入り、強力な薬も効かなくなって来ている。今できることは彼が死を迎えるまで快適にいられることである。
2人目
Bernice Factor(78)。脳卒中患者ファクター夫人。このまま口に呼吸器を付けたままにするか、胸を切開して管を挿入して呼吸器に直接繋げるか決断できない。妻の尻に敷かれた医者の夫や主治医の存在も混乱に輪をかける。
3人目
Manuel Cabra(33)。精巣ガン患者キャプラ氏。抗ガン剤の副作用で肺線維症になるが、心肺不全の原因が薬の副作用であることがなかなかわからない。
4人目
Charlie Sperazza(73)。心臓と肺に疾患を持つスペラーザ氏。心臓が悪いのに医者に行かず、その状態が肺、腎臓、肝臓に負担をかけ、最後は突然倒れて病院に運び込まれる。
参考:http://articles.philly.com/1990-01-28/entertainment/25906038_1_intensive-care-unit-high-tech-medicine-titicut-follies
この4人の病状はどれも深刻で、医師ができることは限られてしまっている。しかし、そのできる範囲の中で決断しなければならない。心臓に直接、管を挿し込んで自主呼吸を試みてもらうか、リスクを避けて呼吸装置に繋いだままにするのか。挿し込んでもダメなら抜くのか、そのままにして死を迎えるのか。このような微妙な決断を患者本人や家族と一緒に決定しなければならないシーンの連続はどれも似通って見えるけど、患者の年齢や家族の精神状態、アメリカでは主治医の存在(!)などによって微妙な差異を見せている。それが6時間の中にしっかりと刻み込まれていた。この長尺の意味はそこにあると云っても良い。
最近では日本でも、この映画に出てくるような医師の病状説明(インフォームド・コンセント)が一般的になって、私も妹が亡くなった時にその場に加わったことがあったので、なおさらこの映画への集中度も違っていた。こんな濃密な6時間を味わうことが出来る映画を作ったフレデリック・ワイズマンの才能をあらためて感嘆せざるを得ない。オールタイムベストの映画に加えてもいいくらいの映画だ。
→フレデリック・ワイズマン→ボストンのベス・イスラエル病院に運び込まれた人びと→アメリカ/1989→シネマヴェーラ渋谷→★★★★☆