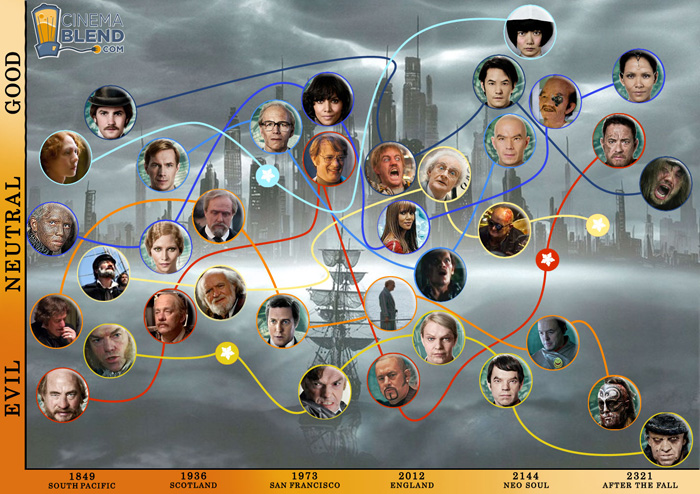監督:三浦淳子
出演:木下愛、木下洋子、木下節子、木下堅固、木下仁、木下綾子、木下雄介、木下美保、吉川結美、吉川和美
制作:クロスフィット、トリステロ・フィルムズ/2012
URL:http://tristellofilms.com/sanagi/
場所:東京しごとセンター5F会議室(みみの会)
不登校になってしまった子どもたちと接する機会がちょっとだけあったりするので、不登校になる理由もさまざまであることは理解しているけど、この映画に出てくる“愛ちゃん”の理由もまたちょっと特殊なパターンだった。おそらく子どもたちがたくさん集まる「学校」と云う場に身を置くことに何かしらの強迫観念を持つようになってしまって、そこへ行くこと自体がイヤになってしまったのではないかと映画を見て想像することができる。だから「学校」と云う場以外では友達となんら問題なく遊んだりすることができる。他人とのコミュニケーションには何の問題もないところが、今まで目にしてきた不登校児とはまったく異なった部分だった。
となると、何が問題なのか見た目には分かり辛く、ただ単純に怠けていると判断して、まわりの大人たちが登校を無理強いさせてしまってますます症状を悪化させてしまう場合もあるのかもしれない。世間ずれしてしまった大人たちは、まだ擦れていない繊細なこころを理解することができなくて、自分たちのありふれた行動様式だけで子どもたちを判断してしまうのかもしれない。でも、そのような繊細な心を持つことは、例えば将来に芸術分野で仕事をして行くとすればとても大切な要素であったりするので、一見マイナス要素に見えてしまう不登校と云う行為をむげに責め立てるのではなく、まわりのものが上手くコントロールしてあげることが重要だ。そのことをこの映画を観て痛感した。この映画の中の大人たちは、なんと上手く“愛ちゃん”を上手く見守ってあげているんだろう。無理強いもせず、かと云って放り出しもせず、ほどよい距離感を保っている姿勢に大変驚いてしまった。
最終的には成人した“愛ちゃん”をも映画は追いかけて行き、まわりの大人たちの適切な庇護のもとに感受性豊かなまま成長し、美術大学に進んでいる姿を映し出す。それを見て、この映画は不登校児を更生させていく姿を追いかけたドキュメンタリーと云うよりは、実際にはもっと包括的に捉えて、子育てとは何なのかを語ったドキュメンタリーであることに気が付いた。説明を抑えた表現方法は、特殊な状況をクローズアップしているわけではないことを示していた。そう考えれば、この映画の意味するところがもっと奥深く、含みが多くなるとおもう。
→三浦淳子→木下愛→クロスフィット、トリステロ・フィルムズ/2012→東京しごとセンター5F会議室(みみの会)→★★★☆