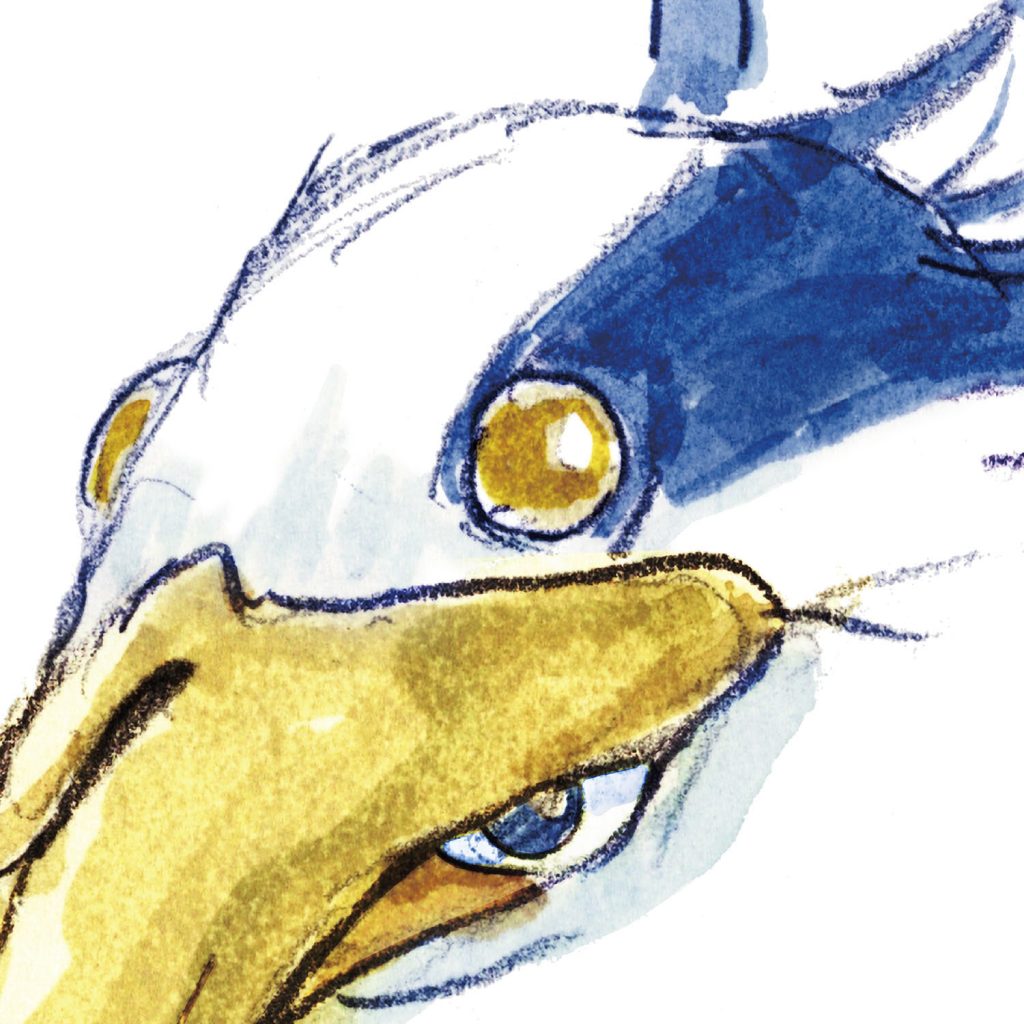監督:グレタ・ガーウィグ
出演:マーゴット・ロビー、ライアン・ゴズリング、ケイト・マッキノン、イッサ・レイ、ハリ・ネフ、アレクサンドラ・シップ、エマ・マッキー、シャロン・ルーニー、デュア・リパ、ニコラ・コクラン、アナ・クルーズ・ケイン、リトゥ・アルヤ、マリサ・アベーラ、キングズリー・ベン=アディル、シム・リウ、スコット・エヴァンス、チュティ・ガトゥ、ジョン・シナ、マイケル・セラ、エメラルド・フェネル、アメリカ・フェレーラ、アリアナ・グリーンブラット、ウィル・フェレル、コナー・スウィンデルズ、ジェイミー・デメトリウ、リー・パールマン、ヘレン・ミレン(ナレーター)
原題:Barbie
制作:アメリカ/2023
URL:https://wwws.warnerbros.co.jp/barbie/
場所:ユナイテッド・シネマ浦和
1959年3月にアメリカのマテル社から発売された女の子向けの人形玩具「バービー」は、日本では1967年に発売されたタカラの「リカちゃん」人形が爆発的な人気を得てしまったために市場に入り込む余地がなくなってしまったけれど、その後もタカラと提携したり、バンダイと提携したりと、日本でもある程度は認知度はある人形玩具になった。
世界中で大ヒットした人形玩具「バービー」だとしても、その映画化を女性たちは観るんだろうかと頭の中にはクエスチョンマークがいっぱいだった。でも、映画館での予告編を観たり、SNSで事前情報を得たりすると、単純なおもちゃに関する映画ではなくて、昨今の時流に合わせたジェンダーフリーに関する映画に仕上げているようなので、グレタ・ガーウィグが監督することもあって観に行くことにした。
女の子が必ずと云って良いほど夢中になる人形玩具と云うものが、人形で遊ぶことが「女らしい」と考える周りの大人たちからの働きかけによることが大きいのだとすると、そのような旧弊な考え方が女性と云うものをある一定の枠に押し込めてしまって、女性の社会進出を阻める役割を担ってきたとも云えるのかもしれない。
このことがこの映画が作られたポイントではないかと考えて観始めた。
マーゴット・ロビーが演じている「バービー」は、女性のために作られた見せかけの理想である「バービーランド」から抜け出て、現実の人間社会でのさまざまな女性たちを見ることによって、自分の置かれている立ち位置を理解して「自立」しはじめる。
と云うようなところまでは考えていた通りだった。
でもグレタ・ガーウィグは、フェミニズム一辺倒の映画にはしなかった。「バービー」に添え物のように存在している男の人形「ケン」からの視点を入れたり、グレタ・ガーウィグが『レディ・バード』でも見せたような母娘の視点を取り入れたりと、そうすることによってもっと総合的な視点からの女性映画に仕上げていた。
最後、人間の世界での生活をはじめた「バービー」が婦人科に行って「婦人科検診に来ました!」と言って映画は終わる。これはいったい何を意味するのかとグレタ・ガーウィグのインタビューを読んだら、
https://www.cinra.net/article/202308-gretagerwig_gtmnm
「バービーが最後にすることはすごく普通なことだから、逆に響くんじゃないかなって考えたんです。」
「あれが勝利だとしたら最高じゃないですか? 勝利のかたちが「普通なことをすること」って。」
と云っていた。なるほどねえ、奥深い映画だった。さすがグレタ・ガーウィグだった。
→グレタ・ガーウィグ→マーゴット・ロビー→アメリカ/2023→ユナイテッド・シネマ浦和→★★★☆