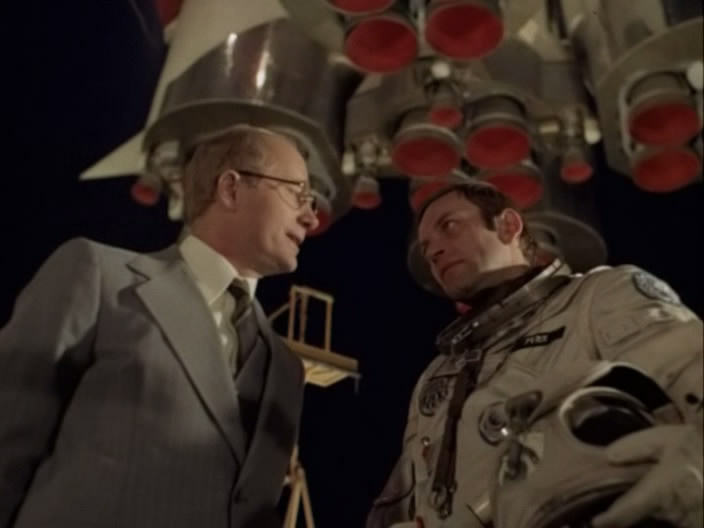監督:エドガー・ライト
出演:アンセル・エルゴート、ケヴィン・スペイシー、リリー・ジェームズ、エイザ・ゴンザレス、ジョン・ハム、ジェイミー・フォックス、ジョン・バーンサル
原題:Baby Driver
制作:アメリカ/2017
URL:http://www.babydriver.jp
場所:T・ジョイ SEIBU 大泉
エドガー・ライトの映画の素晴らしさは、元ネタ探しというオタク的な部分もあるのだけれど、やはり、流れる曲にタイミングを合わせた映像のカット割りのリズムと映画を観ている我々のテンションとがシンクロする心地よさにあるとおもう。今回の『ベイビー・ドライバー』は、それがさらに磨きがかかって到達点に達したんじゃないのかなあ。ファーストシーンのベイビー(アンセル・エルゴート)によるスバル「インプレッサ WRX」のカーチェイス・シーンから始まって、5年後の仮出所で刑務所の前にクラッシックな車「シボレー・インパラ・コンバーチブル」を乗り付けたデボラ(リリー・ジェームズ)を見るまで、映画と一緒に一気に疾走する感覚が気持ちよすぎる。
それから、いつもながらエドガー・ライトの選曲も素晴らしい。主人公の愛称が「ベイビー」であることから、その名称の出てくる曲が数多く流れる(設定としてはiPodから)けど、そんな中でもCarla Thomasの「B-A-B-Y」はいいなあ。いつか、どこかで、聞いたことのある曲。
今年になってスティーヴ・ハミルトンの「解錠師」と云う本を読んだ。子供のころの両親の事件がトラウマとなって口がきけなくなり、その内側に向かうパワーが少年を金庫破りに成長させて、次第に闇の世界に取り込まれて行くストーリーだった。その過程で理想の女の子と出会い、なんとかその闇の世界から抜け出そうともがく設定も含めて、もちろんそっくりとは云わないけど、とてもよく似ていた。エドガー・ライトはこの話をベースにしたんじゃないのかなあ。
→エドガー・ライト→アンセル・エルゴート→アメリカ/2017→T・ジョイ SEIBU 大泉→★★★★