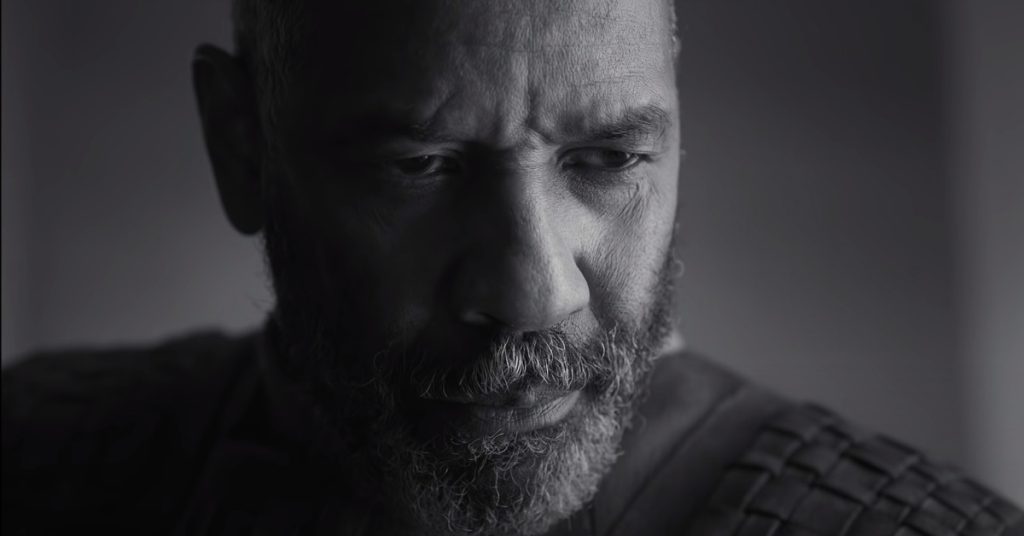監督:ジョン・ワッツ
出演:トム・ホランド、ゼンデイヤ、ベネディクト・カンバーバッチ、ジェイコブ・バタロン、ジョン・ファヴロー、ジェイミー・フォックス、ウィレム・デフォー、アルフレッド・モリーナ、トーマス・ヘイデン・チャーチ、リス・エヴァンス、ベネディクト・ウォン、トニー・レヴォロリ、マリサ・トメイ、アンドリュー・ガーフィールド、トビー・マグワイア
原題:Spider-Man: No Way Home
制作:アメリカ/2021
URL:https://www.spiderman-movie.jp
場所:109シネマズ菖蒲
「スパイダーマン」の映画化は、まずは最初にサム・ライミのトビー・マグワイア版スパイダーマンがあって、そしてマーク・ウェブのアンドリュー・ガーフィールド版スパイダーマンがあって、そして今のジョン・ワッツのトム・ホランド版スパイダーマンの3種類あることになってしまった。なぜ、そんなことになったかをネットで確認してみた。
サム・ライミの最初の3部作が終わったあとに、そのままサム・ライミで『スパイダーマン4』の企画が進んでたのだけれど、どうやら期限までに納得が行く脚本を書けずに、映画製作会社のソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントがしびれを切らして、マーク・ウェブのリブート版に移行してしまったらしい。
https://www.cinematoday.jp/news/N0050977
次のマーク・ウェブの「アメイジング・スパイダーマン」2部作のあとも、そのままマーク・ウェブで『アメイジング・スパイダーマン3』の企画が進んでいたらしいのだけれど、今度はアンドリュー・ガーフィールドの降板(理由は公表されず)で頓挫。次のトム・ホランド版スパイダーマンになったらしい。
https://kaigai-drama-board.com/posts/2949?p=2
まあ、制作会社と監督やキャストとの確執はよくあることで、同じ監督と俳優でシリーズを続けていくことなんて至難のわざと云えなくもない。だから、映画を観る我々も、たとえ3パターンのスパイダーマンがあったとしても、別に怒るようなものでもなんでも無かった。どちらかと云えば、いろんな役者のスパイダーマンが観られて楽しいと感じるくらいだった。
そして、そのトム・ホランド版スパイダーマンが公開されようとしたころ、今度は実写映画版とは異なるアニメ版スパイダーマンの企画が持ち上がった。それは『スパイダーマン:スパイダーバース』として2018年に公開された。ストーリーは、複数ある宇宙の中にいる複数のスパイダーマンが一堂に会すると云うもので、これはおそらくマーベル・コミックの世界観がマルチバース(多元宇宙)であることから来るものではないかとおもう。
このマーベル・コミックのマルチバース(多元宇宙)の考え方からすると、実写版スパイダーマンが3種類あることも、考えようによってはマルチバースじゃね? と云うこと(でしょう?)で、なんとトビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールド、トム・ホランドのスパーダーマン全員が揃う映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』が(密かに?)企画された。
でも、この企画を成功させるカギは、昔のスパイダーマン役であるトビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールド本人が出演してくれることだった。とくにアンドリュー・ガーフィールドは、何かしらの確執でスパイダーマン役を降りたわけだから、果たして出演オファーにOKしてくれるのか? だったろうとおもう。
ところが、それが実現した。アンドリュー・ガーフィールドがなぜオファーにOKしたかは、Varietyのインタビューで言及していた。
https://variety.com/2022/film/news/andrew-garfield-spider-man-no-way-home-1235148458/
On a base level, as a Spider-Man fan, just the idea of seeing three Spider-Men in the same frame was enough.
「基本的なこととして、一人のスパイダーマン・ファンとしても、同じフレームに3人のスパイダーマンが登場するということだけで(出演オファーを受ける理由として)十分でした。」
と云っている。
出演者が興奮するんだから、映画を観るほうも興奮必至だった。くわえて、それぞれの映画の悪役だった、グリーン・ゴブリン役のウィレム・デフォーも、ドクター・オクトパス役のアルフレッド・モリーナも、サンドマン役のトーマス・ヘイデン・チャーチも、リザード役のリス・エヴァンスも、エレクトロ役のジェイミー・フォックスも、すべて本人が出演することになった。
まるで昔の正月映画の、オールスタア・キャスト映画の、怪獣大戦争だった。ああ、オールスタア・キャストと云う響きだけで興奮してしまう。映画会社が俳優を抱えていた昔ならいざ知らず、いまでは俳優ひとりの費用も馬鹿にならないから、そんなに簡単にオールスタア・キャストの映画を作ることは難しいのかもしれない。でも今回の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』が、ひとつの道筋を作ったような気もする。Netflixのアダム・マッケイ『ドント・ルック・アップ』もオールスタア・キャストの様相を呈していることから、今後、配信系の映画製作会社の豊富な資金力を生かして、またオールスタア・キャスト映画が公開されるかもしれない。
いやあ、楽しい映画だった。
→ジョン・ワッツ→トム・ホランド→アメリカ/2021→109シネマズ菖蒲→★★★★