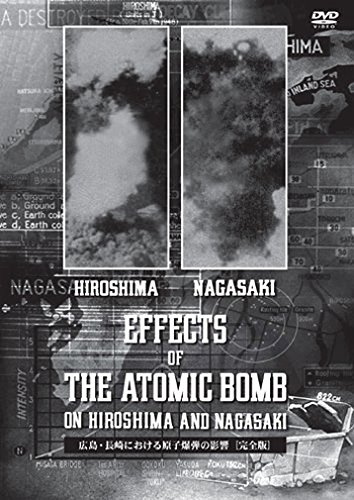監督:森達也
出演:佐村河内守、佐村河内香
制作:「FAKE」製作委員会/2016
URL:hhttp://www.fakemovie.jp
場所:ユーロスペース
2014年に起きた佐村河内守のゴーストライター問題は、彼のことをまったく知らなかったので、一人の人間がどうしてあそこまで罪人のようにマスコミにつるし上げられなければならないのかいまいちよくわからなかった。
おそらく、
・耳が聞こえるのに、聞こえないと嘘をついた。
・まったく作曲ができないのに、自分で作曲していると嘘をついた。
の2つの嘘を元に、不当に自分をイメージアップさせてお金を稼いだ(だまし取った)ことに我慢がならないと云うことなのかなあ。
しかし、ゴーストライターだった新垣隆が楽曲の権利を主張しているわけでもないし、そのCDを買った人は曲の完成度に満足しているらしくて、佐村河内守を「詐欺師」と刑事告発するものでもないらしい。舛添要一と同じように、違法ではないが不適切、らしい。
その佐村河内守を追った森達也のドキュメンタリーは、その2点の嘘を解明することに絞り込んだコンパクトなドキュメンタリー映画だった。
まずは、本当に耳が聞こえないのかどうか。そこを執拗に森達也のカメラは追いかける。でも、耳が聞こえるか聞こえないかなんて、第三者にはその程度はまったくわからない。完全に聴力を失っているのなら明確な診断書が医者から発行されるのだろうけど、微妙な差異は他人には確認しようがない。ただ、一つ云えることは、この問題が明らかになる前に放映されたNHKスペシャル「魂の旋律 音を失った作曲家」では「完全に音を失った」ことを強調し、耳鳴りに悩まされて日常生活にまで支障を来している様子を強調して、佐村河内守の作曲は命を削ってまで行われていることをやたらと視聴者に訴えかけていた。この番組を見た人は、その描写で持って佐村河内守に同情を寄せたかも知れないし、それで佐村河内守を知ってCDを買った人が多数いたのかもしれない。
ところが今回の『FAKE』では「完全に音を失った」ではなくて「音がねじ曲がって聞こえる」に変わっているし、耳鳴りやそれを抑えるために飲む薬についての描写はまったくなかった。NHKスペシャルの時よりも病状が回復しているんだろうか。いや、おそらくは、佐村河内守の耳には何かしらの問題はあるのだろうけど、その程度はNHKスペシャルで描かれたほど酷くはないと云う感じなんじゃないかとおもう。そこに明確な、それでいてささやかな「嘘」が存在するのは確かなような気がする。
次に作曲についてだけど、佐村河内守は新垣隆に丸投げしたのではなくて「共作」であることをやたらと強調していた。その指示書も多数出てくる。自分には音楽的なイメージは湯水のように湧くけど、それを楽譜に起こすことが出来ないので、その部分だけを新垣隆に手伝ってもらっただけだと云う。うーん、曲のイメージを形作ることと実際に音符を書くことの分担が出来て、その作業を「共作」と呼べるのかどうかは音楽的な知識がないのでまったく判断のしようがない。なので、この映画ではその疑惑を素人でも判断できるように、佐村河内守がシンセサイザーを購入して作曲するシーンをラストに持ってきた。おお、作曲できるじゃん、とは一瞬おもったけど、でもこれ、ただの打ち込みだよなあ、とすぐさま冷静になる。これを持ってして、彼の非凡な作曲能力が示される訳ではなくて、ただただ、フツーに打ち込みをする姿が映し出されるだけなのですべてが微妙なままだった。
この森達也のドキュメンタリーは「佐村河内守を信じる」宣言をして、一緒に泥舟に乗って漕ぎ出しているような構成にはなっているので、ラストに佐村河内守が作曲をするシーンを持ってくることによって、どうだ、佐村河内守は白だろう、と訴えかけているような作りになっていた。しかし、森達也が云っている「ドキュメンタリーは嘘をつく」をすぐさま思い出した。ああ、これは確信犯だな、と。本当は、佐村河内守のことを白だなんてまったく考えてないと。それがエンドクレジット後の佐村河内守への問いかけにかいま見える。おお、そこがタイトルの『FAKE』なのか!
いやいや、とても面白い映画でした。
→森達也→佐村河内守→「FAKE」製作委員会/2016→ユーロスペース→★★★★