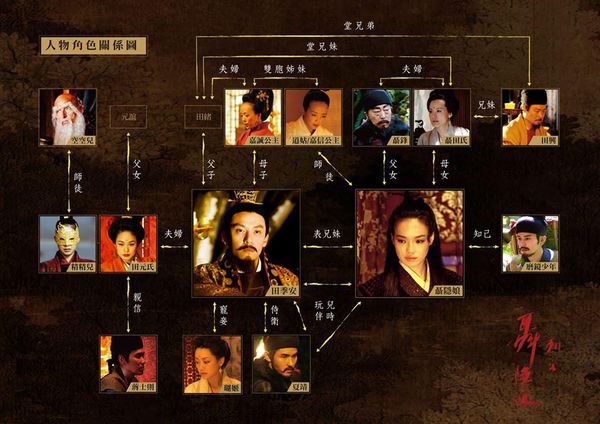山形国際ドキュメンタリー映画祭。今日観た映画は以下の通り。
●アレクサンダー・ナナウ監督『トトと二人の姉』(Toto and His Sisters、ルーマニア、2014)
ロマ人はルーマニア社会でも最下層に位置するらしく、仕事の無いロマの若い奴らは四六時中クスリばっかりを射っている。それをそのままカメラに収めている部分に引っかかるところがあるけど、それが現実だとしたらやはりそのままカメラに収めるべきだともおもうし。最下層から抜け出すには周りのサポートが大切なのに、刑務所から出所したばかりの母親のダメさ加減が見えて映画が終わるところに絶望感が。トトがヒップホップダンスの才能で最下層から抜け出せることを願うばかり。
●イェレヴァント・ジャニキアン、アンジェラ・リッチ・ルッキ監督『東洋のイメージ ― 野蛮なるツーリズム』(2001)
●マノエル・ド・オリヴェイラ監督『ニース ― ジャン・ヴィゴについて』(1983)
二つともインスタレーションに近くて、椅子に縛られて観るものではなかった。もっと自由に観るべき映画だった。
●ペドロ・コスタ監督『ホース・マネー』(Horse Money、ポルトガル、2014)
ポルトガルのカーネーション革命のこととか、元ポルトガル領だったカーボベルデのこととか、ポルトガル関連の知識が乏しいとなかなか理解することの難しい映画だった。不安を駆り立てるような映像や音響効果だけはしっかりと伝わって来たけど。